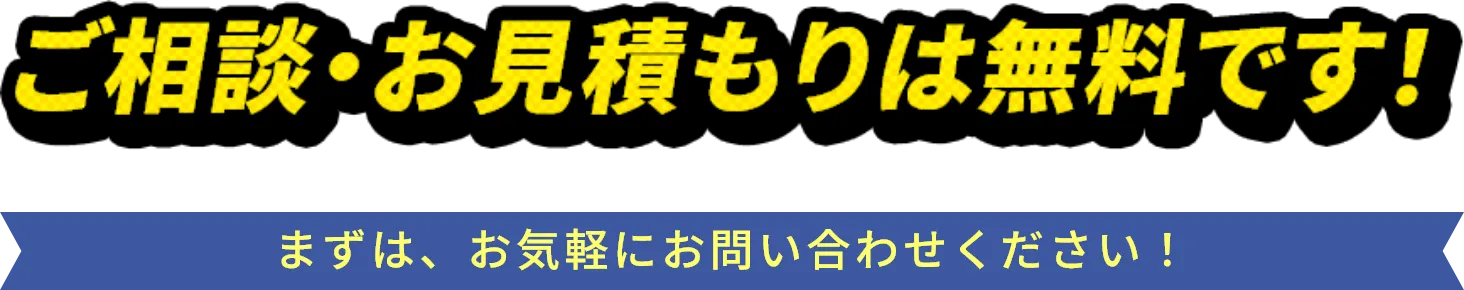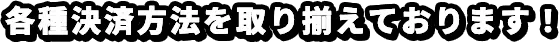荷造り・梱包の方法
お引越し作業をスムーズかつ安全に行うためには、効率的な荷造りと梱包がポイントです。荷物の種類や使用頻度を考慮し、無理なく整理することで、お引越し後の片付けもスピーディーになるため、ぜひご参照ください。
このような荷物は
お客様ご⾃⾝で
運んでください!
現⾦・貴⾦属・鍵・
通帳等の貴重品、
冷蔵⾷品・卵などの
冷蔵庫の生もの
(ペット・家電製品のリモコンは、可能な限りお客様にてお運びください)
正しいダンボールの
組み⽴て⽅
1底板を折り込む
ダンボールの底面をしっかり折り込み、四隅が浮かないように整えます。
※折り込みが不十分だと底が抜ける原因になります。
2テープで中央を固定
底面の中央にテープを貼ります。「I貼り(一の字貼り)」で、しっかり固定します。
3十字貼りで補強する
重い荷物を入れる場合は、テープを十字に貼って底面をさらに補強します。
※「I貼り(一の字貼り)」や、「クロス組み」は底が抜けることがあり危険です。
※「H貼り」は運搬時に滑りやすく、落下破損につながります。

このような梱包は
避けてください

ヒモがけ・
ヒモ結び

袋詰め

箱の盛上がり

底の組込み
※ワンタッチ式は除く
お引越しの荷造りの
進め⽅
step.
不要品を処分する
お引越しの荷造りは、不要品の処分から始めましょう。家の中を見渡し、必要なものと不要なものをしっかり分けてください。壊れているものや使えなくなったものはもちろん、今後使う予定がないものや買い替えを予定しているものも、この機会に思い切って処分するのがおすすめです。
不要品の処分は、お引越しの1カ月前を目安に始めましょう。自治体の粗大ゴミ回収サービスなどを利用する場合、申し込みから回収までに時間がかかることがあります。スケジュールに余裕を持って早めに手配しましょう。リサイクルショップやフリマアプリを利用して売却する方法もありますが、手間と時間がかかるため、計画的に進めることが重要です。

step.
荷物をグループ分けする
次に、荷物を種類ごとにグループ分けしましょう。「キッチン用品」「バス用品」「本・書類」「子どものおもちゃ」など、用途や使用場所に応じてまとめておくと、新居での荷解きがスムーズになります。
特に割れ物は、別の箱にまとめて梱包し「ワレモノ注意」と赤字で大きく記載しましょう。食器や瓶類、電子機器などは、緩衝材をしっかり使用して包むことで破損を防ぎます。また、荷解き時に混乱を避けるため、箱の表面には内容物の詳細を記載しておくと便利です。

step.
お引越し日まで
使わないものを梱包する
お引越しの2週間前あたりに、お引越し日まで使わないものから順に梱包を始めましょう。荷物の量が多い場合は、毎日少しずつ梱包を進めると効率的です。
以下のようなものは、早めに荷造りしても問題ありません。
- オフシーズンの衣類や寝具
- 季節家電(暖房器具、扇風機など)
- 買い置きしてある日用品(トイレットペーパー、洗剤、シャンプーなど)
- 買い置きしてある食品(乾麺、缶詰、レトルト食品など)
- 趣味のアイテムやインテリアグッズ
- 本、CD、DVD

step.
まだ使う可能性のあるものをダンボールに入れる
お引越し当日まで使う可能性のあるものは、ダンボールに入れても封をしないでおきましょう。必要になったときにすぐ取り出せるようにするためです。例えば「賃貸契約書などの重要書類」「工具や掃除道具」「文房具や日常的に使うアイテム」などの荷物は、お引越しの前日または当日に封をするのが理想的です。

step.
お引越し当日に全ての
ダンボールに封をする
日常的に使うアイテムは、お引越し当日に梱包する必要があります。以下のものは、最後に梱包するアイテムの例です。
- 衣類
- 布団
- 食器・調理器具
- 衛生用品(歯ブラシ、シャンプー、ティッシュペーパーなど)
- スマートフォンや各種デバイスの充電器
お引越しの2日前には、前日と当日に着る服を確保し、残りの衣類を梱包しましょう。また、お引越し前日・当日の食事は外食やお弁当を利用することで、調理器具や食器の梱包を早めに済ませることができます。

小物関係

茶碗
茶碗は、新聞紙や緩衝材を使って全体をしっかり包むように梱包しましょう。他の食器と直接接触すると欠ける恐れがあるため、露出部分がないよう注意が必要です。茶碗同士がぶつからないように1つずつ包み、隙間にはさらに緩衝材を詰めると安心です。

お皿
新聞紙や緩衝材で1枚ずつ丁寧に包みます。お皿は上からの力に弱いため、ダンボールには縦に立てて収納するのがポイントです。ダンボールの底にタオルや緩衝材を敷き、運搬中の衝撃を和らげるよう工夫しましょう。

コップ・グラス
新聞紙やエアキャップ(プチプチ)を使って全体を包みます。広げた緩衝材の上にコップやグラスを置き、下から上へ折り返して包みます。その際、余った部分を内側に折り込むことで、内側もしっかり保護できます。割れやすいので、ダンボールの中で動かないように隙間を緩衝材で埋めるとより安全です。

刃物類
刃先が露出しないようにしっかり梱包しましょう。ダンボールを二つ折りにして刃先を包み、ガムテープで固定する方法がおすすめです。また、新聞紙やタオルで刃先を巻き、さらにビニール袋に入れておくと、より安全に運搬できます。ダンボールには「刃物注意」と記載しておくと、荷解き時の事故防止になります。

キッチン用品・
カトラリー類
キッチン用品やカトラリー類は、まとめてビニール袋に入れると便利です。特にキッチン用のハサミやスライサーなどの鋭利なアイテムは、緩衝材で包んだうえでビニール袋に入れるようにしましょう。細かいアイテムは小分けしておくと、新居での整理が楽になります。

鍋・フライパン
重さのある鍋やフライパンは、重いものを下、軽いものを上にしてダンボールに収納します。まずダンボールの一番下にフライパンを入れ、その上に鍋や鍋蓋を重ねましょう。各アイテムの間に新聞紙やエアキャップを挟むことで、運搬中の傷や衝撃を防げます。また、ダンボール内の隙間にも緩衝材を詰めて、中身が動かないようにしましょう。

調味料
調味料は、運搬中に中身がこぼれないようにキャップをテープで固定したり、ラップで包んで輪ゴムで留めたりします。そのうえで、まとめてビニール袋に入れておきましょう。瓶入りの調味料は割れやすいため、新聞紙やエアキャップで包んで保護します。また、液漏れのリスクを考え、瓶同士がぶつからないように緩衝材をしっかりと使いましょう。
家電製品

大型家具
そのままの状態では搬出・搬入が難しい場合、事前に解体しておくのがポイントです。ネジや金具などのパーツは、紛失しないようチャック付きの袋にまとめて保管しましょう。引越業者によっては、家具の解体・組み立てサービスを提供している場合もあるので、必要に応じて利用を検討すると良いでしょう。

本棚・食器棚
荷造りの前に中身を全て空にします。大型の棚は搬出・搬入が難しいこともあるため、事前に解体が必要な場合があります。解体した場合は、ネジや金具などのパーツをチャック付きの袋にまとめておきましょう。また、棚板や扉も緩衝材で保護しておくと安心です。

映像機器・
オーディオ機器
テレビやオーディオ機器は、振動や衝撃による故障リスクが高いため、引越業者が専用の梱包を行うことが一般的です。事前に配線を外し、まとめておくとスムーズです。また、新居での接続時に困らないよう、配線を外す前にスマートフォンなどで写真を撮っておくことをおすすめします。

パソコン
パソコンは運搬中に故障やデータ消失のリスクがあります。お引越しの前に、重要なデータは必ずバックアップを取っておきましょう。ノートパソコンの場合は、荷物に入れずに手荷物として運ぶとより安全です。デスクトップパソコンの場合は、モニターと本体をそれぞれ緩衝材で包み、衝撃を防ぐように工夫しましょう。

小型家電
トースターや炊飯器、電子レンジなどの小型家電は、ダンボールに入れて隙間に緩衝材を詰めると安全に運搬できます。掃除機や加湿器などのダンボールに収まらない家電については、引越業者が梱包を行う場合があります。電源コードはまとめて固定し、運搬中に絡まないようにしておきましょう。

冷蔵庫
お引越しの前に中身を空にし、水抜きと霜取りの作業を行う必要があります。水抜きは製氷機や蒸発皿に溜まった水を取り除く作業で、霜取りは庫内に付着した霜を溶かして拭き取る作業です。これらの作業は、お引越しの前日に行うと良いでしょう。運搬後に再び使用する際は、庫内が完全に乾燥していることを確認してから電源を入れましょう。

洗濯機
荷造りの前に給水ホースや排水ホースの水抜きを行います。水抜きをしないまま運搬すると、内部に残った水が漏れる恐れがあります。通常、お引越しの前日に水抜きを行い、その後は使用を控えます。ホース類は外してまとめ、ビニール袋に入れておくと便利です。

仏壇・仏具
繊細なパーツが多いため、運搬時に特に丁寧な対応が必要です。引越業者によっては、仏壇の運搬に追加料金が発生する場合があります。また、宗派に応じた供養や儀式が必要になることもあるため、事前に確認しておくと安心です。仏具は個別に緩衝材で包み、破損や紛失を防ぎましょう。
タンス類・その他

洋服タンス・
衣装ケース
洋服タンスは中身を空にしておきます。衣装ケースについては、衣類のみであれば中身を入れたまま運搬できる場合もありますが、引越業者によって対応が異なるため、事前に確認しましょう。また、タンスの引き出しや扉は、ガムテープで固定する必要はありません。ガムテープを貼ると、剥がす際に表面を傷めてしまうことがあるためです。

布団
布団や毛布、枕などの寝具は、布団袋を使用して梱包します。まず床に布団を広げ、布団袋をその上から被せたら、上下をひっくり返して袋に収めます。最後に紐でしっかりと結べば梱包完了です。布団袋がない場合は、大きめのダンボールやビニール袋を代用しましょう。

ベッド
ベッドは、搬出の際にフレームの解体が必要になることがあります。その場合は、ネジや金具は小さな袋にまとめ、部品ごとにラベルを付けておきましょう。解体したフレームやマットレスは、引越業者が専用の資材を使って梱包することが一般的ですが、事前に緩衝材や毛布で保護しておくと安心です。また、搬入先の間取りを確認し、ベッドがスムーズに搬入できるか確認しておきましょう。

ソファー
搬出前にカバーを外し、布製の場合は洗濯しておくと清潔に運べます。座面や背もたれ部分が取り外せる場合は、分解しておくと搬出がスムーズです。角や足の部分は、運搬中の傷を防ぐために緩衝材でしっかり保護しましょう。皮革製のソファーは、専用のクリーナーで汚れを拭き取ったうえで、保護カバーを掛けると安心です。
引越はヨイナミッチャク
0120-417-389
営業時間 9:00~20:00 年中無休